社会情報学部
社会情報学科
SCHOOL OF SOCIAL INFORMATICS
SAGAMIHARA CAMPUS
文・理の領域をつなぎ、融合した学びを通じて
現代社会に必要な考える力と実践力を養う
- MENU -
MOVIES 動画で知る社会情報学部
-
社会情報学部 授業紹介
-
寺尾 敦教授 マルチメディア学習論
-
村田 和義教授 ヒューマンインタフェース
NEWS 社会情報学部ニュース
-

EVENT
2024.4.16【社会情報学部】青山・情報システムアーキテクト育成プログラム 中級コース(ADPISA-M)
-

EVENT
2024.4.16【社会情報学部】青山・情報システムアーキテクト育成プログラム 上級コース(ADPISA-H)
-

NEWS
2024.3.25【社会情報学部】杉村篤哉さん、森陽菜さん、萩野直人さん、藤田然さん(ともに社会情報学部4年、松澤芳昭研究室所属)が「情報処理学会 研究会/全国大会」で受賞
-

NEWS
2024.3.21【社会情報学部】宮治研究室所属の黒川皇輝さん、CHEN CHENGさん、佐島拓さん、鵜木綾子さんが「Open Hack U 2024 TOKYO」にて最優秀賞を受賞
-

NEWS
2024.3.21【社会情報学部】河内日向乃さん、工藤亜美さん、比留間圭輔さんが「情報コミュニケーション学会 第19・20回全国大会」にて優秀発表賞を受賞
-

NEWS
2024.3.4【社会情報学部】青山・情報システムアーキテクト育成プログラム(ADPISA)が「BA賞2023」を受賞
OVERVIEW 数字で見る社会情報学部
- 男女比
- 58:42
- 学生数(定員)
- 220 名
- 進路決定率
- 90.7 %
CONCEPT つなげよう。無限の可能性へ。
-
数学的思考は重要ですが、理工系レベルの専門的数学は求めません。
数学を学ぶ目的は、「論理的なものの考え方」を身につけることです。
それは、これまで文系のものとされてきた「人や社会の問題」は、
いまや科学・情報技術の活用なくしては解決できないからです。
本学部では、経済・経営、心理・教育分野志望の人が必要とされる数学を教えます。 -
文系志望でも、安心して学べます。
本学部教員の約半数は、情報・数理に理解のある人文社会系の研究者です。本学部は、基本的に人文・社会系への発展的なプログラムが中心となるため、文系志望でも安心して学ぶことができます。
-
理工系志望でも、発展的に学べます。
これまで理系が担ってきた「科学・情報技術の活用」は、いまや理系だけでは進展困難な状況にあります。社会や人の問題解決を抜きにしては、何も進めないからです。本学部教員の約半数は、人や社会に目を向けた理工系研究者であるため、より現実的な学習を進めることができます。また、情報・数理分野についても、発展的なプログラムを提供します。
-
実践で使える英語力が身につけられます。
まず、1年次の英語では発音から学び、リスニング、スピーキングを重点的に鍛えます。なぜなら意思を伝え合うコミュニケーションには、正確な発音が欠かせないからです。その後、年次が進むごとに、ライティング、リーディングの力を伸ばしていきます。また、TOEIC®などの検定試験対策や、専門分野と直結したプログラムの提供など、“使える英語”の習得を支援します。
PICK UP LECTURES 授業紹介
-
社会情報ナビゲーション
卒業時にどんなことができるようになっているのかを体験する1年次必修の演習授業です。出口のイメージを明確にすることで、これから始まる様々な授業が何のためにあるのかを理解し、学習意欲を高めることがこの授業の目的です。
-
コンピューティング実習
初級プログラミング体験を通して、コンピュータを使った問題解決「コンピューティング」の技法を学ぶ、1年次必修の演習授業です。上位学年で応用可能なプログラミングの基礎を学び、コンピュータを利用した問題解決法をデザインします。
-
Integrated English
1年次での週2回の英語の授業では、前期にr e c e p t i v eな技能(Grammar、Reading)を、後期にproductiveな技能(Speaking、Listening、Writing)を徹底的に学習します。授業外でも英語に触れられるように、e-learningを積極的に導入しています。
-
統計入門
1年次必修の科目です。データのあふれた現代社会では、そうしたデータを整理して有益な情報を得るために、統計学の知識が大いに役立ちます。すべての学生が統計学の素養を持って卒業していくことは、本学部の特色のひとつです。
-
社会数理
高等学校「数学III」に続く微分積分を学びます。様々な量やその変化を取り扱い、数理的な分析に基づいた問題解決を行うためのスキルが身につきます。数学は苦手だけど好きな学生向けにこの科目を学ぶための準備として「社会数理入門」も用意されています。
-
プロジェクト演習入門
グループワークの方法を、実際にプロジェクトに取り組むことを通して段階的に学ぶプロジェクト型授業です。ビジネスマナー、発想法、図的問題解決といった基礎を学んだあと、プロジェクトを遂行し、成果をプレゼンテーションします。
-
プロジェクト演習
実社会での現実の問題に取り組むプロジェクト型授業です。神奈川県経済同友会の会員企業が提示した具体的な経営課題に取り組む、神奈川産学チャレンジプログラムなどに参加します。この授業を通して「創造的協調作業のつぼ」を会得します。
-
合理的思考と社会行動
社会、人間、情報の各分野から複数の教員が協力して作り上げるコラボレーション型授業です。現代社会での問題を取り上げ、専門の異なる教員がそれぞれの立場から講義した後、公開ディスカッションを行い、多角的な視点から問題を理解します。
PICK UP SEMINARS ゼミナール紹介
-
社会現象の異分野融合研究:計算社会科学入門
大林ゼミ本研究室では、社会学を核として分野融合的に社会現象の謎(メカニズム)を解明することに取り組みます。具体的には、格差問題、介護問題、ネット上でのサイバーカスケードや分極化といった多岐にわたる社会的な謎を、社会学だけではなく心理学、経済学、政治学、情報科学の知識や技術(実験・ビッグデータ解析・数理解析・シミュレーションなど)を駆使しつつ解明する姿勢を身に付けます。
-
経済学的な視点からエネルギーと環境の持続可能な発展を考える
石田ゼミ経済発展、エネルギー消費、地球温暖化の相互関係を考慮しつつ、持続的な発展を可能とする諸条件等について政策面や経済学の観点から考察します。担当者が調べてきたことに対して皆で疑問点を出し合い、議論をします。施設見学を通し、エネルギー供給の難しさを実感します。学生自らが研究テーマを設定し、卒業研究を完成させることは簡単ではないですが、良い経験になっているようです。
-
メディア情報学・メディア情報処理
伊藤ゼミメディア情報学・メディア情報処理は、観光、異文化コミュニケーション、認知科学、心理学、社会科学、医学、教育、社会学などの多様な学問領域と様々な文脈で関わっています。本研究室では、特にピクトグラムという情報表現メディアに注目し、プログラミング、コンテンツ生成・処理、情報デザイン等々について研究しています。学際的にテーマを取り扱う社会情報学部の研究らしさを追求しています。
-
情報通信技術を活用し、 問題を解決する役に立つ 新しいサービスを創る
宮治ゼミ社会の問題を解決するために、情報と社会の双方からアプローチしています。情報技術的な側面として、センシング・画像処理・拡張現実・機械学習を使用したウェブやモバイル開発を身につけます。社会的な側面として、ネットと密接に関わるコミュニティやサービス、マーケティングを学習・調査しています。これらにより、自らサービスを企画し、自らの作り上げられる人材育成を目指しています。
-
ローカルなコミュニティとグローバルな社会構造をつなぐ
香川ゼミ地域の遊び場やコミュニティとタイアップしたイベントを例年、企画しています。日頃から、バンドや作曲をしている学生、サッカー経験者、けん玉がプロ並み…等々、既にどの学生も何らかの多様性を持ち合わせています。それらを上手に組み合わせることで、地域の人たちに喜んでもらえるオリジナルの企画を目指します。そして、この小さな活動を通して、グローバルな社会の課題や仕組みも学びます。
-
スポーツ科学・コーチング・トレーニング科学
遠藤ゼミ遠藤ゼミでは、競技者やコーチの活動に対する理解を深め、アスリートのパフォーマンス向上に役立つ知を得ることを目標に活動しています。経験知(身体知)と科学知との融合、理論と実践との循環、課題解決型の思考体系・思考力、実践内容の計画性と創造性、などの観点からスポーツを学際的に紐解いていくことを目指す活動を礎に、スポーツの価値を多面的に追求していく姿勢を大切にしています。
FROM STUDENTS 卒業生・学生インタビュー
-
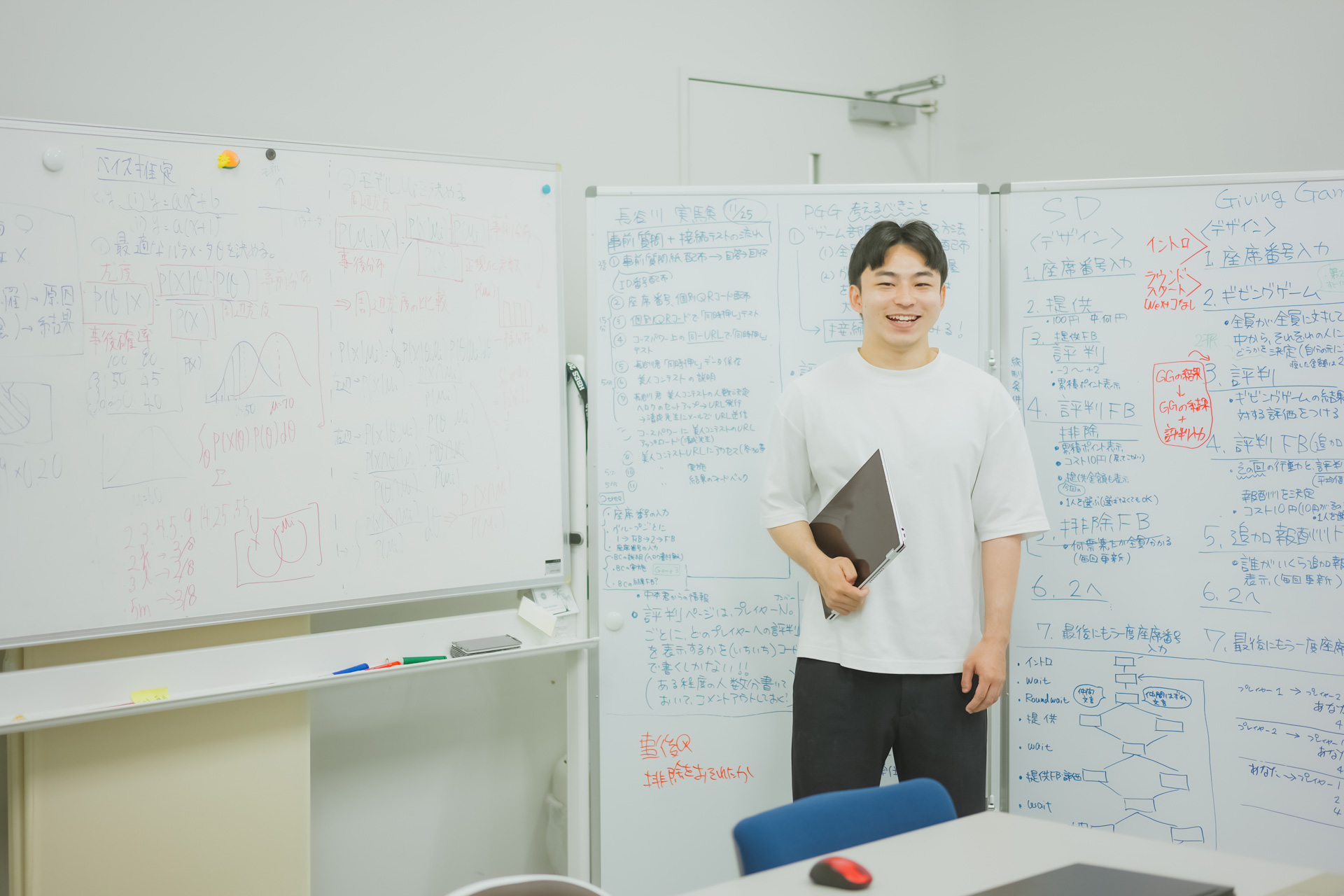 比留間 圭輔 社会情報学研究科社会情報学専攻社会情報学コース博士前期課程
比留間 圭輔 社会情報学研究科社会情報学専攻社会情報学コース博士前期課程「社会心理学」の研究を 続け、受賞に輝く。この先は磨いたスキルを 生かし、社会に貢献を
(2023/10/26 公開)比留間 圭輔 社会情報学研究科社会情報学専攻社会情報学コース博士前期課程 -
 関根 蒼真 社会情報学科
関根 蒼真 社会情報学科<2023年度 学業成績優秀者表彰 最優秀賞受賞>
友人へのライバル心が転機に前向きに学び成績アップ、インターンシップ先でも高評価
(2023/9/12 公開)関根 蒼真 社会情報学科 -
 越河 虹哉 社会情報学科
越河 虹哉 社会情報学科漠然とした興味を打ち込める専攻分野と将来の仕事につなげた理想の4年間
(2023/8/31 公開)
越河 虹哉 社会情報学科 -
 吉田 智彦 社会情報学研究科 社会情報学専攻 博士前期課程修了
吉田 智彦 社会情報学研究科 社会情報学専攻 博士前期課程修了ビジネスに変革をもたらすDX。ユーザーのニーズをくみ取り成功への道筋を描く
(2023/2/22 公開)吉田 智彦 社会情報学研究科 社会情報学専攻 博士前期課程修了 -
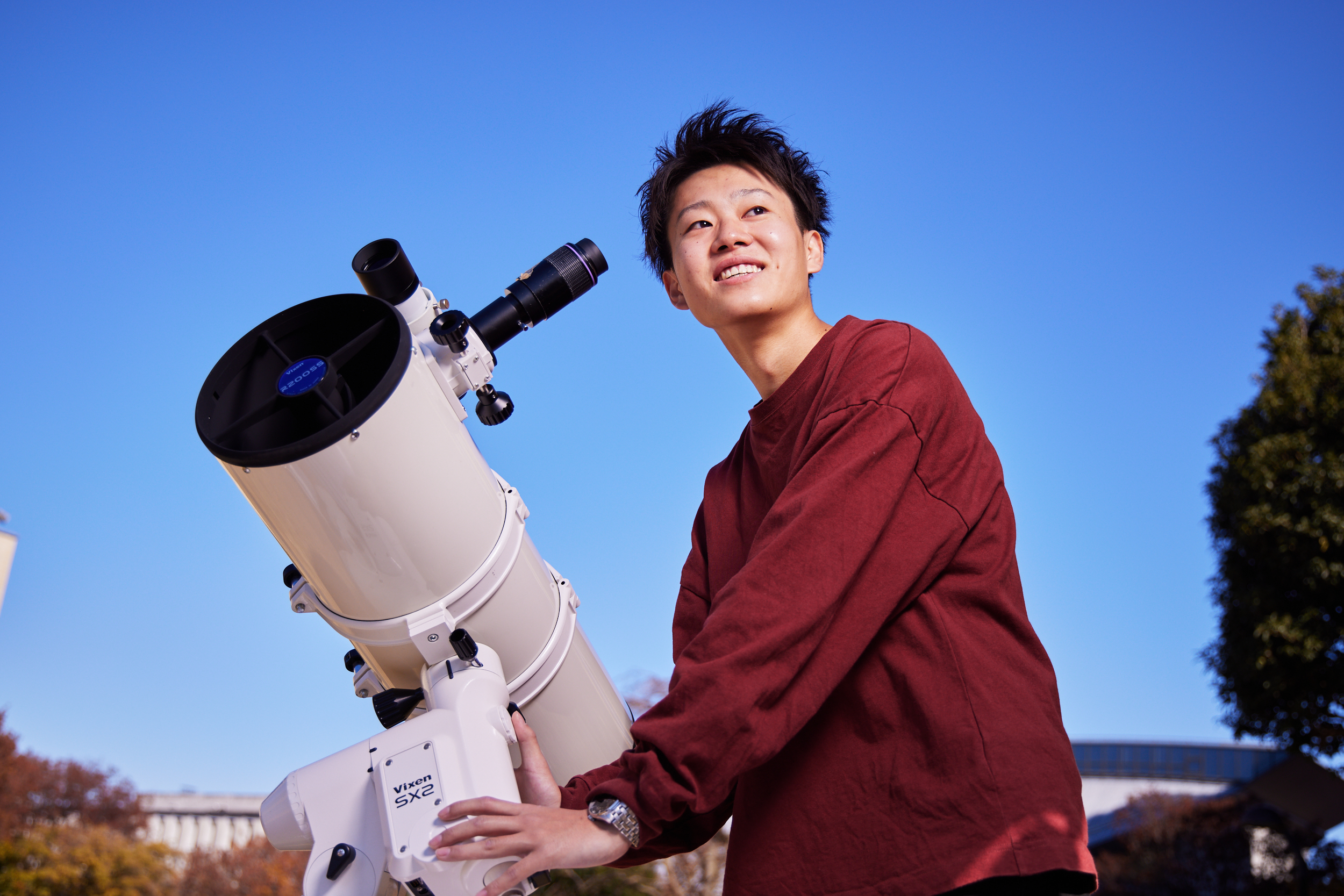 寺内 龍太 社会情報学科
寺内 龍太 社会情報学科ふたつの活動を掛けもちし、組織マネジメントのスキルや企画力が向上
(2023/1/25 公開)寺内 龍太 社会情報学科 -
 川畑 友理恵 株式会社 NTTデータ
川畑 友理恵 株式会社 NTTデータ情報と社会をつなぎ顧客の望みの一歩先を見据えるITのスペシャリストに
(2022/12/22 公開)
川畑 友理恵 株式会社 NTTデータ -
 物部 柚香 社会情報学科
物部 柚香 社会情報学科<2022年度 学業成績優秀者表彰 最優秀賞受賞>
社会に役立つものづくり。成功から自信を、失敗からは強さを得た
(2022/9/2 公開)物部 柚香 社会情報学科 -
 森本 千香子 社会情報学科
森本 千香子 社会情報学科学際的・実践的な学びにふれて見出した将来の目標
(2021/7/16 公開)森本 千香子 社会情報学科 -
 深井 駿介 社会情報学科
深井 駿介 社会情報学科銀行内定のカギはコミュニケーション力とオンライン面接対策
(2021/1/13 公開)深井 駿介 社会情報学科 -
 笛田 桃 社会情報学科
笛田 桃 社会情報学科新聞編集委員会での経験が学生生活を彩り、就活へとつながった
(2021/1/6 公開)笛田 桃 社会情報学科
FROM FACULTY MEMBERS 教員・研究室インタビュー
-
 伏屋 広隆 教授 社会情報学科
伏屋 広隆 教授 社会情報学科お金に関する人々の行動メカニズムを紐解き、金融市場の安定化へ
(2023/5/18 公開)伏屋 広隆 教授 社会情報学科 -
 寺尾 敦 教授 × 並木 翔平 社会情報学科
寺尾 敦 教授 × 並木 翔平 社会情報学科あらゆる分野で必要となるデータに基づいて考えるスキルを磨く
(2022/11/15 公開)寺尾 敦 教授 × 並木 翔平 社会情報学科 -
 宮治 裕教授 × 薄井 百花 社会情報学科
宮治 裕教授 × 薄井 百花 社会情報学科「つくる」にこだわり、ICTと工学システムの力で社会問題を解決する
(2023/10/24 公開)
宮治 裕教授 × 薄井 百花 社会情報学科 -
 大宮 謙 教授 社会情報学科
大宮 謙 教授 社会情報学科青山スタンダード
社会貢献を現場と教室で学ぶ「サービス・ラーニング科目」
(2022/5/31 公開)大宮 謙 教授 社会情報学科